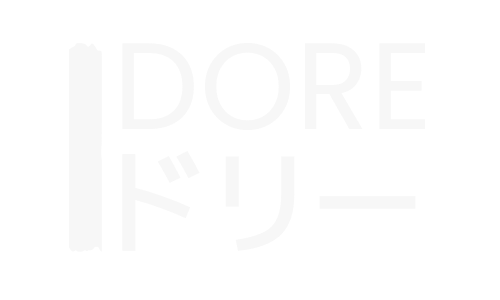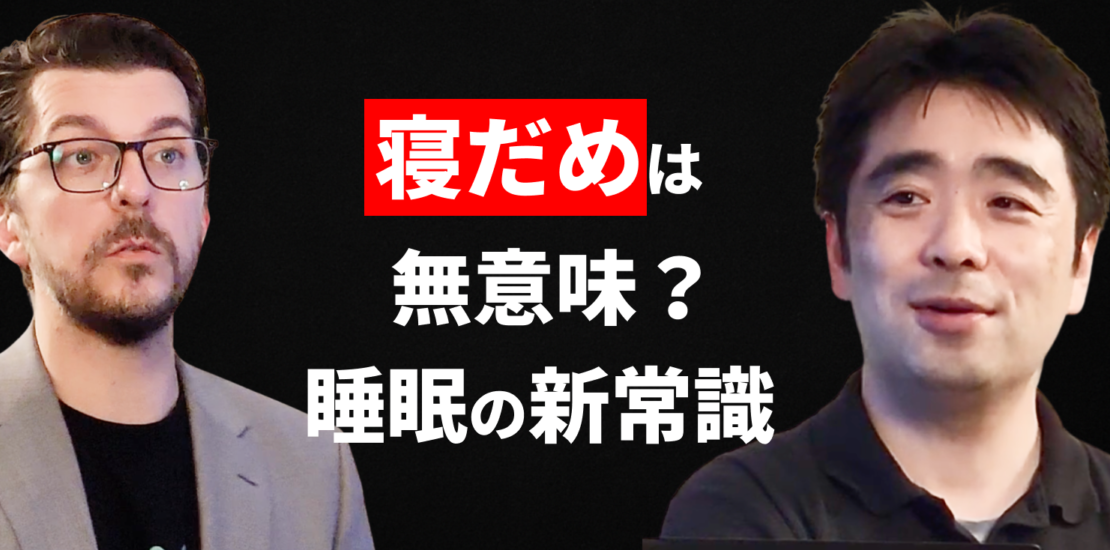睡眠は「休むだけの時間」ではありません。創造性や判断力を上げるための投資です。
東大発の睡眠ベンチャー・株式会社ACCELStarsの知見をもとに、個人と会社がすぐ使えるやり方を整理しました。
本稿では、睡眠の見直し方、体内時計の整え方、データの使い方、現場での運用、文化づくりまでをやさしく解説します。
- ゲスト紹介

飯田 悠祐
アクセンチュアでコンサルタントを務めた後、グリーやリクルート住まいカンパニーなどで新規事業・プロダクトを牽引。MICINでは国内最大級のオンライン診療サービスを統括し、事業開発やアライアンスを担う。2021年12月より株式会社ACCELStars役員。
2. 本論セクション
2-1. 失敗を招く思考:「睡眠=休息だけ」は危険
寝不足で働くと、論理をつかさどる前頭前皮質が疲れ、感情をつかさどる扁桃体のブレーキが弱くなります。イライラしやすく、相手の話を咀嚼したり、気持ちをくみ取ったりする力が落ちます。サービス業のように対人接点が多い仕事ほど、顧客満足や売上に直結します。だからこそ、睡眠を“成果の先行指標”として扱い、計画・投資・評価の中に最初から入れておく発想転換が必要です。
2-2. 成功の鍵:KPI化と“小さな成功”の積み上げ
まずは効果が見えやすい行動から始めます。たとえば「起床時刻を毎日そろえる」「就寝前のスクリーン時間を短くする」「朝の強い光を浴びる」。週に一度、睡眠の記録とミス率・対応品質などを一緒に見て、変化を共有します。「睡眠を整えると日中の集中が上がる/ミスが減る」という事実が見えると、現場のやる気と継続率が上がります。
2-3. チーム設計:体内時計をそろえる
人には朝型・夜型の違いがあります。全員に同じ生活を強いるより、「毎日同じ時刻に起きる」を共通ルールにする方が効果的です。週末の“寝だめ”は体内時計を乱し、月曜の不調を招きます。朝の強い光で体内時計をリセットし、就寝1〜2時間前の入浴で深部体温を一度上げてから下げる流れをつくると、入眠しやすくなります。昼寝は事故やミスの予防として短く取り、夜の睡眠の代わりにはしません。
2-4. 人選:個人差を尊重し、データで確かめる
勝ちパターンは人それぞれです。押しつけず、選べる改善策を提示できる人が推進役に向いています。主観だけで判断せず、計測データと行動記録で手ごたえを確認する姿勢が大切。短期の数値だけでなく、数週間単位の変化も合わせて見ましょう。
2-5. 現場ドリブン:非デスク層にも届く運用
現場スタッフの状態がパフォーマンスに直結します。ルールは「誰でも迷わず実行できる」ようにシンプルにし、伝え方も分かりやすくします。たとえば、昼寝の位置づけ(ミスの予防であって夜の代替ではない)や、就寝前のデバイス使用が体内時計を遅らせることなど、要点をはっきり示します。日々のコミュニケーションでは、良い変化が出たときに具体的に言葉で認めると定着が進みます。
2-6. 文化と制度:睡眠を軽んじない空気をつくる
「睡眠軽視は基本的人権の侵害に等しい」という考え方があります。徹夜や寝不足を美徳にしないことが重要です。起床時刻の固定や光の取り入れ方など、会社として睡眠不足を解消する協力体制を整えましょう。安心して取り組める空気が、組織全体のパフォーマンスを底上げするはずです。
2-7. 外部環境×戦略:日本の事情とデータ活用
日本は世界的に見て睡眠時間が短いと言われています。長い通勤などの社会的要因も影響します。だからこそ、主観に頼らず、時計型デバイスで実睡眠時間やレム/ノンレムの状態を客観的に把握し、飲酒・入浴時刻といった行動アンケートと合わせて改善ポイントを特定しましょう。会社に提供するのは個人が特定できない形の傾向データにとどめ、プライバシーを守りながら組織的に改善するべきです
3. チェックリスト
[ ] 起床時刻を毎日そろえる(週末も同じ)
[ ] 朝いちで強い光を浴びる仕組みを作る
[ ] 就寝前の画面時間と明るさのガイドを配布
[ ] 入浴は就寝1〜2時間前に済ませる
[ ] 週次で睡眠記録と業務指標を一緒に見る
[ ] 非デスク向け掲示・朝礼スクリプト・1on1の型を整える
睡眠を「休む」から「高める」へ。体内時計の管理とデータの見える化で、個人も組織も底上げできます。まずは小さな一歩を決め、毎週の振り返りで効果を確認しましょう。先行指標(KPI)としての睡眠を、人事と事業の中心に据えることが近道です。
フルエピソード:休日の寝だめは無意味?睡眠の新常識
https://www.youtube.com/watch?v=V_YbKgL64AE