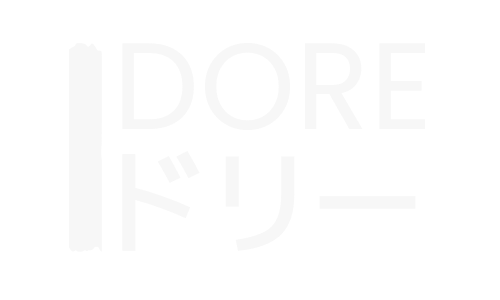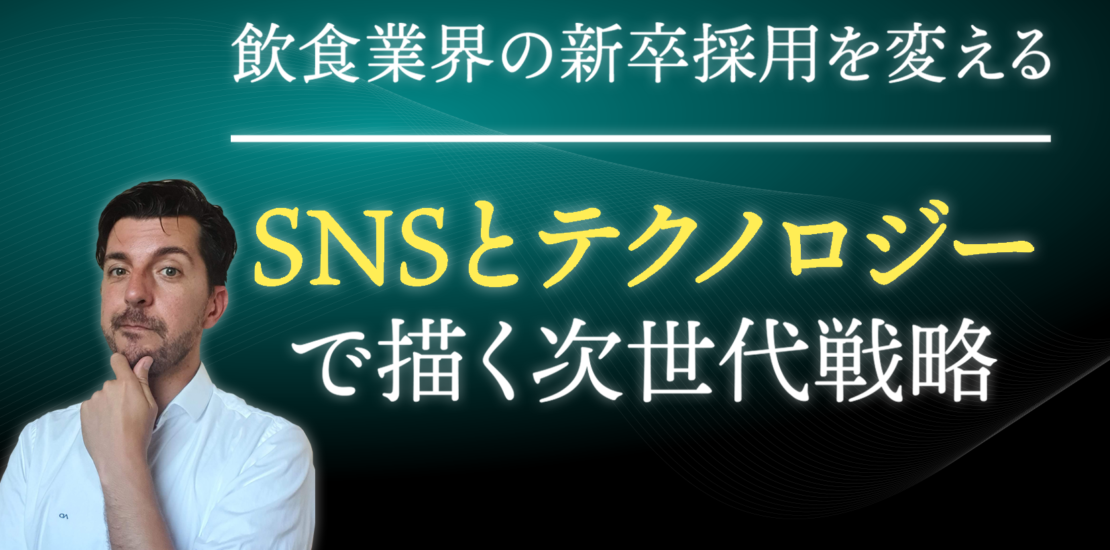私は先日、とある大手フードサービス企業の担当者とお会いしました。病院や学校、大企業の社食など数多くの拠点を運営する彼らは、毎年300名の新卒を採用することを目標としています。しかし、ここ数年は応募者数そのものが減少し、昨年は必要数の半分ほどしか集まらなかったとのこと。日本の若年層人口は厚生労働省の統計でも減少が続いており、15~24歳の人口は過去20年で約30%も減ったともいわれています。こうした人口減少の影響と、若者がSNSなどを通じて多様な働き方を知る時代背景が重なり、いま新卒採用は大きな転換期を迎えています。
飲食業界の新卒採用における現状と課題
実際に「飲食 新卒 採用」と検索すると、上位に表示される記事の多くは、若年層の応募を獲得するために「企業理念やビジョンの可視化」や「SNSを使ったブランディング強化」を推奨しています。特に飲食業界では、給与面や労働時間のイメージから若者が敬遠するケースが少なくありません。そのうえ、Starbucks(スタバ)などの有名コーヒーチェーンなど、より「オシャレ」なブランディングを展開する企業も、同じ層をターゲットとしているため、競合が激化しています。私が会ったフードサービス企業の担当者も、「どうすれば若者に魅力的に映るか」を真剣に模索していました。
テクノロジーの活用で採用効率を高める
こうした課題に対し、多くの企業がデジタル技術の導入を進めています。たとえばAIを搭載したApplicant Tracking System(ATS)を用いて応募者を一括管理すれば、初期選考の効率化やデータに基づく採用戦略の立案が可能になります。実際、Freedman & Companyの調査によると、日本企業のSNS広告費は昨年比で30%増加しているとのこと。応募者の母集団を広げるために、InstagramやTikTokなど若者が多く利用するSNSで積極的に露出を増やす企業が増えているのです。
さらに、オンライン説明会やウェブ面接の導入も進んでいます。これにより、応募者は自宅や大学から移動せずに参加できるため、企業説明会への参加率が高まり、採用コストの削減にもつながります。
SNSとコミュニティで若者を惹きつける
一方で、テクノロジーだけでなく、“企業らしさ”を若者に共感してもらう仕組みづくりも重要です。先述のフードサービス企業に対しても、私は「SNSでのブランディングを強化すること」と「社員が働く様子をわかりやすく見せること」を提案しました。たとえば制服をトレンド感のあるデザインに変えたり、社員同士が仲良く働く姿をInstagramやTikTokで発信することで、若者が「ここで働きたい」と思えるイメージを醸成するのです。
実際に「飲食 新卒 採用」に関する記事でも、SNSでの積極的な発信や社内イベントのレポートなど“リアルな雰囲気を伝える情報”の重要性が指摘されています。若い世代は給与や福利厚生も重視しますが、「仲間とのつながり」や「社会に貢献している実感」に強く惹かれます。彼らが自分のSNSで職場の写真をシェアすることで、自然と企業の宣伝にもなっていくのです。
ユーザー目線の採用プロセス設計を
ここで鍵となるのが、いわゆる“ユーザー中心設計”の考え方を採用活動にも取り入れることです。たとえば応募フォームをスマホでサクッと入力できるようにしたり、面接のスケジュールを柔軟に設定したりすることで、応募者の負担を減らせます。Recruit Holdingsの調査でも、入力項目を最小限に絞ることで応募完了率が20%向上したとのデータが示されています。
さらに、キャリアパスや研修制度を明確に示してあげることも大切です。単に「飲食店で働く」といっても、経営企画やマーケティング、海外進出など多彩な道があるかもしれません。その可能性を伝えることで、「自分が成長できる場所」という期待感を持ってもらえるのです。
サービス業界が今後取るべきアプローチ
最終的には、テクノロジーの活用と“人間らしさ”の両立が勝敗を分けると感じています。AIやSNSでの発信をフル活用する一方で、若者が何を大切にしているかをしっかり理解することが必要です。私が提案しているのは、「おしゃれな制服」や「職場のコミュニティ感」を高める施策、そして「社会貢献度をわかりやすく示す」ことです。こうした取り組みによって、フードサービス業界やその他のサービス業でも“仕事を通じて仲間と成長し、社会に貢献できる場所”という魅力を十分にアピールできるはずです。
競合の激化や人口減少といった厳しい現実はあるものの、逆に言えば企業の工夫次第で新卒採用を成功へ導く余地はまだまだあります。テクノロジーを効率化の手段として使いつつ、SNSとコミュニティづくりで若者の心をつかむ。そこにユーザー目線での採用プロセス設計を組み合わせれば、飲食業界をはじめとするサービス業に再び大きな人材の流れを呼び込むことも、決して夢ではないと私は考えています。