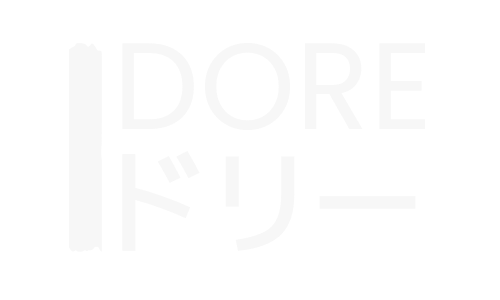私は現在、ソフトウェア会社の社長をやっていますが、実はもともとデザイナーでした。特にプロダクトデザインを中心に活動していて、「インタラクションデザイン」の仕事をしていました。今は「デザイン思考」という言葉で知られています。今日はその「デザイン思考」についてお話ししたいと思います。
デザイン思考を知らない方や聞いたことがある方、自社でも取り組んでいるという方、いろいろだと思いますが、デザイン思考で大切なのは「いい商品、ヒット商品、多くの人が使う商品を作りたい」という目的です。なぜデザイン思考が重要かというと、「ミスをする可能性を減らす」ことができるからです。
商品開発では大きく分けて3つのアプローチがあります。
1つ目は「会社中心」のアプローチです。
例えばソニーがスピーカーを作っていて、そこからウォークマンのような関連商品を開発するという考え方です。会社が既に持っている資産をベースに商品を作ります。
2つ目は「技術中心」のアプローチです。
例えば富士フィルムが持っているケミカル技術を活用して化粧品を開発したり、ソニーのカメラセンサーをヘルスケアに応用したりするケースです。
3つ目は「ユーザー中心」のアプローチです。
ユーザーが抱える課題に注目し、その課題解決のために必要な技術や分野を後から考えます。実際のビジネスでは、この3つを組み合わせて使うことが多いですが、デザイン思考では特に、この「ユーザー視点」を重要視します。
ユーザー視点とは、商品を使う人がどんな人なのか、どんな生活をしているか、家族や趣味、社会環境まで深く理解することから始まります。また、最初から明確なゴールを決めすぎるのではなく、問題を探しながら徐々に解決策を見つけることが重要です。
よくある失敗例として、以下の3つがあります。
- ビジネスや技術の担当者がデザイン思考のプロセスに最初から参加しないこと。
- フィールドワーク(ユーザー調査)が不足していること。
- 最初から作りたい商品が決まっており、その正当化のためにデザイン思考を利用しようとすること。
私自身の経験を話すと、ソニーのバイオシリーズで「BRICs向けの商品」を開発する際、ブラジル、中国など各地でフィールド調査を行いました。その結果、若者が音楽を非常に重視していることを発見し、それを基に音質に特化したパソコンを開発しました。この商品は、音楽を重視していたブラジルやインドでは成功しましたが、音楽を重視していなかった日本では、あまり売れませんでした。
デザイン思考のプロセスは次のようになります。
- 分野とターゲットを決める
- ユーザー調査を行う
- ペルソナを作成する
- ユーザージャーニーマップを作成する
- コンセプトをブレインストーミングで考える
- プロトタイプを作る
- プロトタイプを基に再びユーザー調査をする
- 商品を開発・リリースする
- 振り返りをして次のバージョンを考える
大切なのはこのサイクルを繰り返すことです。デザイン思考という名前自体は重要ではありませんが、このプロセスを踏むことで失敗の可能性を大きく下げることができます。
何か質問や知りたいことがあれば、ぜひコメントをください。次回もお楽しみに!